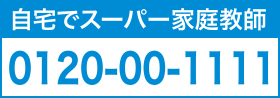新着情報
新着・更新情報などをご案内します
入試で役立つ化学 蒸気圧降下と沸点上昇、凝固点降下について
2025年10月11日
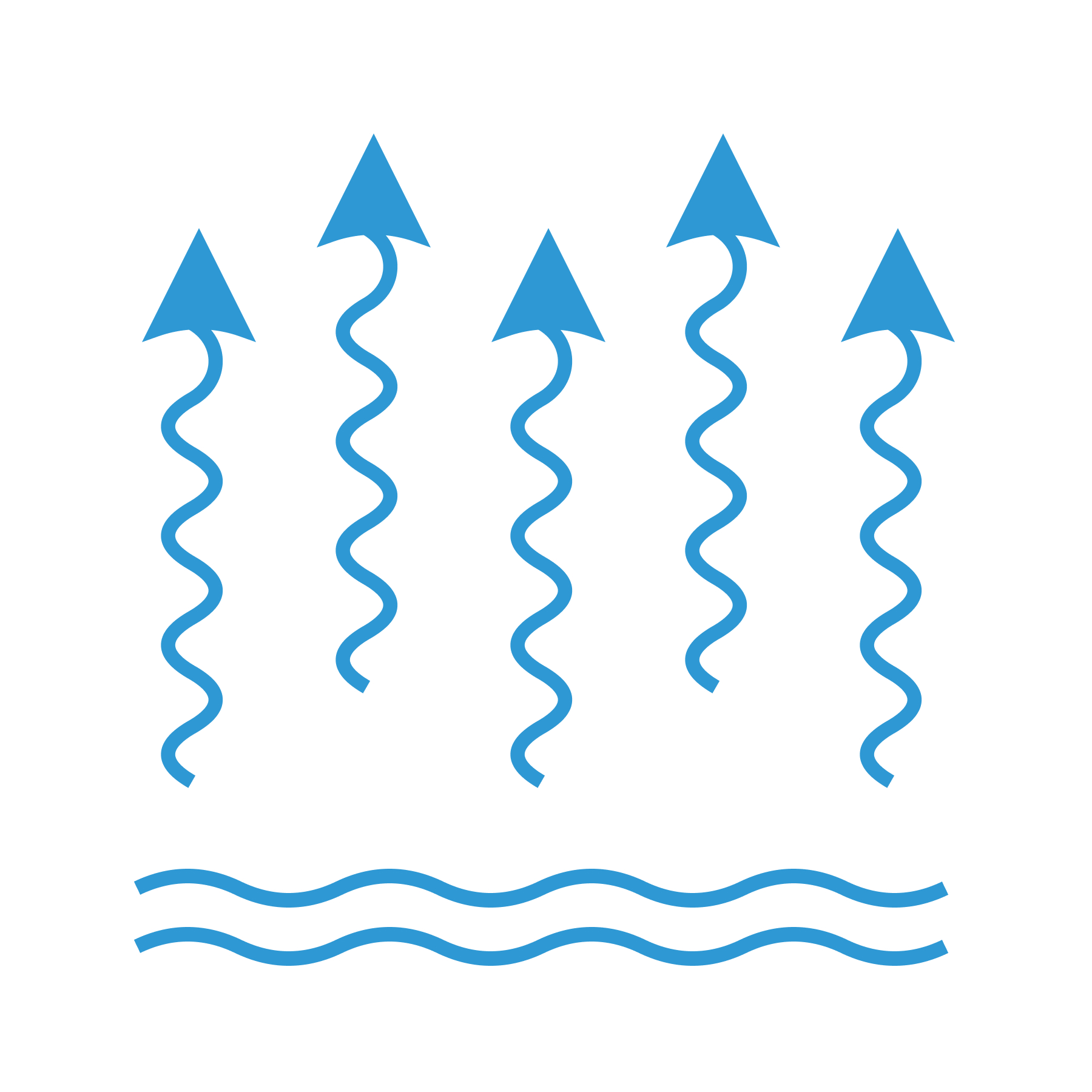
今回は蒸気圧降下と沸点上昇、凝固点降下について書いておこうと思います。
前回の記事はこちら→(入試で役立つ化学 シュウ酸について)
蒸気圧降下について触れる前に、蒸気圧について復習しておきましょう。
例えば、密閉容器に水を入れておくと、やがて単位時間に蒸発して水蒸気になる速度と、逆に水蒸気から凝縮して水になる速度が等しくなって、実際には変化が起きているにもかかわらず、見かけ上蒸発が止まって見える状態になります。この状態を気液平衡といいます。
蒸気圧とは気液平衡のときの気体の圧力を言い、飽和蒸気圧とも言います。この状態は、液体が存在してもこれ以上気体の量が増えない飽和状態になっています。
わずかでも液体が存在して液体と気体が共存する場合は気液平衡状態になります。純粋な液体の蒸気圧は温度よって決まっていて、温度が高くなると、蒸気圧も高くなります。
教科書には、温度と蒸気圧のグラフ(右上がりの曲線)がありますが、このグラフの曲線を蒸気圧曲線と言います。ジエチルエーテル、エタノール、水の3本の蒸気圧曲線が載っていますので、よく見ておきましょう。
この中では、ジエチルエーテルが蒸発しやすく、水が蒸発しにくいことがわかると思います。また、蒸気圧=外気圧となる温度がそれぞれの物質の沸点になります。
ちなみに、蒸発と沸騰は、液体が気体に変化するという点では同じですが、蒸発と沸騰はそれぞれ、蒸発は液体の表面から、沸騰は液体の内部から気化することを言います。
さて、水のような純溶媒と水に塩化ナトリウムやスクロースのような不揮発性物質を溶かした溶液では蒸気圧に違いが出ます。純溶媒と溶液では、溶液の方が蒸気圧が低くなります。この現象を蒸気圧降下といいます。
これは、純溶媒の表面はすべて溶媒分子であるのに対して、溶液の表面は一部が蒸発しにくい溶質粒子で占められていますから、溶液では表面から蒸発する溶媒分子が純溶媒に比べて少なくなり、蒸気圧が低くなります。これが、蒸気圧降下が起こるしくみです。
純粋な水に濡れた布と海水に濡れた布ではどちらが乾きやすいですか?という質問があります。海水より純溶媒の方が水分子が蒸発しやすいので、答えは純粋な水に濡れた布になります。
ここではもう一歩踏み込んで、純溶媒に比べて溶液では蒸気圧がどのくらい下がるのか、簡単に定量的な考察をしてみます。
ラウールの法則
ここで登場するのが、ラウールの法則です。ラウールの法則は、厳密には「理想溶液」(溶質粒子と溶媒分子の相互作用が溶質粒子同士、溶媒分子同士と同程度である溶液)について成り立つのですが、高校化学で扱う希薄溶液ではこの法則が成り立つとして問題ありません。
この法則によると、溶液の蒸気圧=純溶媒の蒸気圧x(1-溶質のモル分率)となります。
また、溶質のモル分率=溶質の物質量/(溶媒の物質量+溶質の物質量)ですが、希薄溶液では、溶質の物質量が溶媒の物質量に比べて非常に少ないため、溶質のモル分率=溶質の物質量/溶媒の物質量とします。
以上から、
溶液の蒸気圧降下度=純溶媒の蒸気圧-溶液の蒸気圧
=純溶媒の蒸気圧-純溶媒の蒸気圧x(1-溶質のモル分率)
=純溶媒の蒸気圧×溶質のモル分率
=純溶媒の蒸気圧×(溶質の物質量/溶媒の物質量)
となります。
ここで、質量モル濃度を思い出してください。
質量モル濃度の求め方は、質量モル濃度=溶質の物質量/溶媒の質量で、質量と物質量は比例しますから、溶液の蒸気圧降下度は溶液の質量モル濃度に比例するといえます。これは、液体の表面における溶質粒子の物質量すなわち個数の割合によって蒸気圧降下の度合いが決まることを定量的に表しています。
蒸気圧降下によっておこる現象に、沸点上昇と凝固点降下があります。純溶媒より溶液の方が、沸点は上昇し、凝固点は降下するという現象です。
沸点上昇について考えてみますと、溶液では純溶媒より蒸気圧が下がる、すなわち先ほど述べた蒸気圧曲線が下方にシフトすることになります。そのため、蒸気圧=外気圧となる温度は上がることになります。教科書では蒸気圧曲線のグラフを用いて説明されています。確認してみてください。
沸点上昇や凝固点降下は、理論化学でよく出題される分野ですが、ポイントは二つあります。
一つは、蒸気圧降下度が質量モル濃度に比例したように、沸点上昇度や凝固点降下度も質量モル濃度に比例します。この時の比例定数は溶質によらず、溶媒によって決まる定数になります。つまり、同じ溶媒であれば何を溶質粒子として溶かすかにはよらないということになります。
もう一つは、溶質粒子の種類に関係なく、物質量すなわち個数に比例する点です。つまり、溶媒分子に溶かしたときに電離してイオンに分かれる電解質であれば、総イオンの物質量に比例するということになります。
例えば、溶質として塩化ナトリウムを用いて水溶液を調整すると、塩化ナトリウム1モルは水に溶けてナトリウムイオン1モルと塩化物イオン1モルの合計2モルの粒子に電離しますから、沸点上昇度が2倍になることになります。ここのところは、よく理解しておきましょう。
このように、粒子の種類によらず、粒子の数が同じならば同じ効果を示すことを「束一的」と言います。高校化学で「束一的」なのは、蒸気圧降下、沸点上昇、凝固点降下、浸透圧です。いずれも計算するときには、粒子の種類によらず、各粒子の物質量の合計を用いて、計算することになります。特にイオンに電離する電解質を溶かした溶液には注意しましょう。
冬季の山道では、よく凍結防止のために、白い粒子状の塩化カルシウムが散布されているのを見かけます。1モルの塩化カルシウムは水に溶けると、1モルのカルシウムイオン、2モルの塩化物イオンに電離しますから、凝固点降下度が3倍になり、凝固点を下げて凍結を防止するのには効率がいいです。
逆に、溶媒に溶かしたときに物質量すなわち個数が減少する例もあります。例えば、酢酸です。酢酸分子は有機溶媒中では、2分子が水素結合をして存在しています。これを2分子会合と言いますが、溶液の中で2分子が1分子のようにふるまうので、見かけの個数すなわち物質量が1/2に近くなります。
最後に、沸点上昇、凝固点降下、浸透圧の計算式には物質量があるので、これらのデータを測定することで、分子量を算出することができます。
沸点上昇、凝固点降下は不揮発性物質で分子量の小さい物質の分子量測定に向いています。また、実験では温度変化を伴うので、温度変化で分解したりする物質には向きません。
一方、浸透圧は高分子化合物など分子量の大きい物質の分子量測定もできます。
(甲府駅北口校N.S先生)
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
この先生の指導を受けてみたい!と思った方はこちらからお申込みください!!