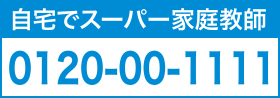新着情報
新着・更新情報などをご案内します
令和7年度山梨大学入試問題・数学の解説と分析
2025年10月25日
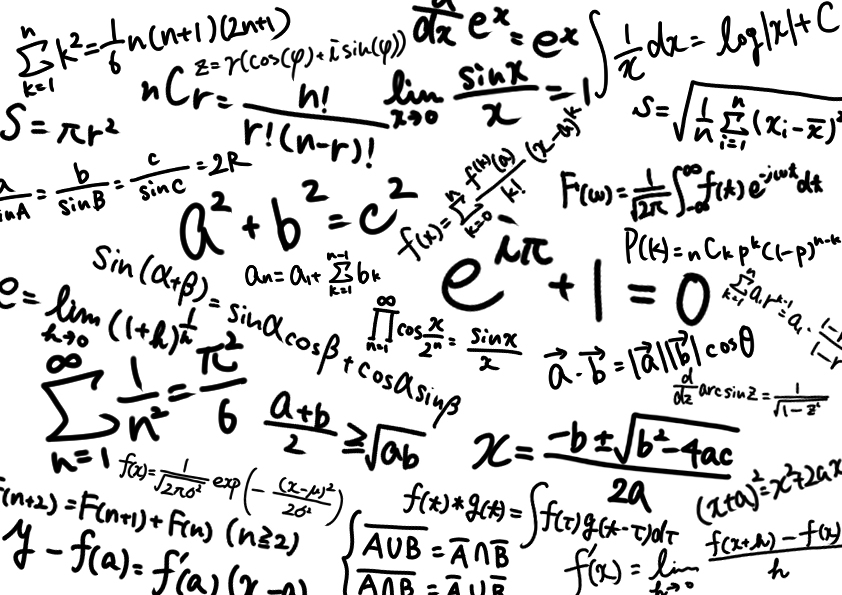
みなさん、こんにちは。今日は山梨大学入試問題・数学の解説と分析をお伝えします。問題と答えは大学のサイトに掲載されていますので、各自で確認して解いてみることをお勧めします。
【工学部・生命環境学部(数学1A2B3C)】
大問1
(1)二次関数がある区間で常に正となる条件を導き、それを座標平面上に図示する問題でした。二次関数の最小値が正ということに気付けるかがポイントでした。
(2)二次方程式が異なる2つの実数解を持ち、実数解を正接tanで置き換えて、加法定理を使う問題でした。加法定理を使うまではよかったものの、その取りうる値の範囲を求めることが困難だったかと思います。aの分数関数と見て値域を求めるとスムーズに解けます。
(3)過去問で頻出の積分計算です。被積分関数が「log×多項式」なので、部分積分を使うという発想は容易だと思います。
大問2
(1)まず、内分点のベクトルの公式からベクトルCPを求め、辺OAと CPが垂直であることを中心に攻めていくと良いです。
(2)点Dが三角形OCPの外接円上の点であるとき、∠OCP=90°よりOPは外接円の直径であることを捉えられるかがまず大事です。そうすると、∠ODP=90°より線分PDと辺OBが垂直であることを使うとuが求まります。
大問3
(1)共通な接点を持つ共通接線の問題です。共通な接点のx座標を文字で置き、接点でのy座標が同じ、微分係数が同じであるという方程式を2つ立てて解きましょう。
(2)y軸の周りに1回転させてできる立体の体積の問題です。数値も難しくなく、グラフの概形が分かれば苦労はしません。
(3)(2)で求めた体積をaの関数としてみたときの最大値問題です。微分すればいいかなという発想になるでしょう。
大問4
(1)単に積の微分を用いるのみです。
(2)被積分関数が「指数関数×三角関数」ですので、部分積分で同型出現を狙っても良いですが、(1)の結果を使うとスムーズに解けます。
(3){In}が等比数列であることを示すには、まずは、In+1とInの関係式を導き、比の値が定数であることを示せば良いでしょう。
(4)(3)から公比が絶対値が1より小さいので、無限等比級数が収束するのは明白でしょう。その和も計算が容易です。
【教育学部・生命環境学部(数学1A2BC)】
大問1
(1)数学1の三角比と数学Aの平面図形の融合問題です。接弦定理に気付けるかがポイントでした。
(2)確率と三角関数の問題です。条件式に値を入れながら実験をしてみると1/2をすぐ超えるので、余事象を捉えられたかがポイントです。
(3)相関係数の定義を覚えている方はラッキー問題です。表など書きながら、計算ミスのないように進めたいです。
大問2
(1)xの恒等式なのでx=1を代入するとaが求まります。その後、左辺はxの関数なので、両辺xで微分すると答えが出ます。
(2)積分区間が定数なので、定積分は定数と置いて解く戦法を理解していると解けます。被積分関数に絶対値がついているので、区間を分けて丁寧に絶対値を外して計算してください。
(3)すでに定数分離されている形なので、大人しくy=g(x)とy=bとの共有点が3個になるようなbの範囲を求めてください。
大問3
工学部・生命環境学部の大問2と同じです。
まとめ
数学3を含め、かなり典型的な問題が多く出題されています。チャートなどで典型的な問題の解法を理解していき、すぐに扱えるように演習を積み重ねましょう。
(韮崎駅前教室 R.T先生)
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
この先生の指導を受けてみたい!と思った方はこちらからお申込みください!!