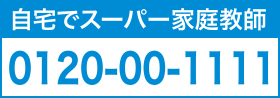新着情報
新着・更新情報などをご案内します
古典文法解説⑧~古文の勉強法について其の二~
2025年05月03日

前回(古典文法解説⑦~古文の勉強法について~)に続いて、今回も古文の勉強法についてお話しします!古文を勉強するとき、「何をどう学べばいいの?」と悩む人も多いと思います。そんな人の手助けになれば嬉しいです。
1. 活用ってなに?
まずは「活用の種類」を覚えてほしいんですが……その前に、「活用」ってそもそも何のことかわかりますか? 簡単に言うと、「単語の形が変わること」です。たとえば、動詞「咲く」を見てみましょう。 「咲かない」「咲きます」みたいに、「く」の部分が「か」や「き」に変わってますよね。これが活用です。このとき、変わらない部分を「語幹(ごかん)」、変わる部分を「活用語尾(かつようごび)」といいます。 「咲く」なら、「咲」が語幹、「く」が活用語尾になります。こうしてみると、私たちって普段の会話でも無意識に活用を使ってるんですよね。 (無意識にやってることを理屈で考えるのって、意外と難しい!)
2. 活用形ってどう決まるの?
活用の仕組みがわかったら、次は「活用形」がどう決まるのかを見ていきましょう。「未然形」「連用形」など、活用には6つの形がありますが、これは自由に使えるわけじゃありません。 文法って、やっぱりルールを理解するのが大事なんです。ポイントは、「活用形は、下にどんな言葉がくるかで決まる」ということ。 たとえば、動詞の後ろに「ず」がつくときは未然形を使います。どの形かわからなくなったら、まずは後ろにある言葉に注目してみてください!
3. 活用の種類を覚えよう
活用の種類を覚えるときは、それぞれの「特徴」に注目するのがコツ。たとえば「四段活用」は、ア段~エ段まで使うから四段活用。 「上二段活用」はイ段とウ段の2つが出てくるから「二段」なんですね。名前の中にヒントが入ってることが多いので、そこを意識して覚えるとわかりやすいですよ!本当はこのあと「活用の種類の見分け方」とかも話したいんですが……ちょっと長くなってきたので、今回はここまで!
🔍今回のまとめ
- 「活用」っていうのは、単語の形が変わること。変わらない部分=語幹、変わる部分=活用語尾!
- 活用形は、好きに使えるわけじゃなくて、「後ろに何がくるか」で決まる。
- 活用の種類は、名前にヒントがあるので、それぞれの特徴をつかんで覚えよう!
古文の文法はちょっととっつきにくいけど、仕組みがわかればぐんと楽になります!少しずつ、一緒にマスターしていきましょう〜!
🌸最後にひとこと!🌸
「この先生の指導を直接受けてみたい!」そんなふうに思ってくれた高校生の皆さんは、ぜひ無料体験授業にお申込みください!勉強の楽しさ、分かる喜びを一緒に味わいましょう!お申込みはこちら!