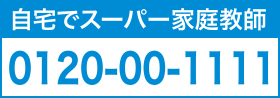新着情報
新着・更新情報などをご案内します
古典文法解説⑥~「に」の識別編~
2025年02月28日
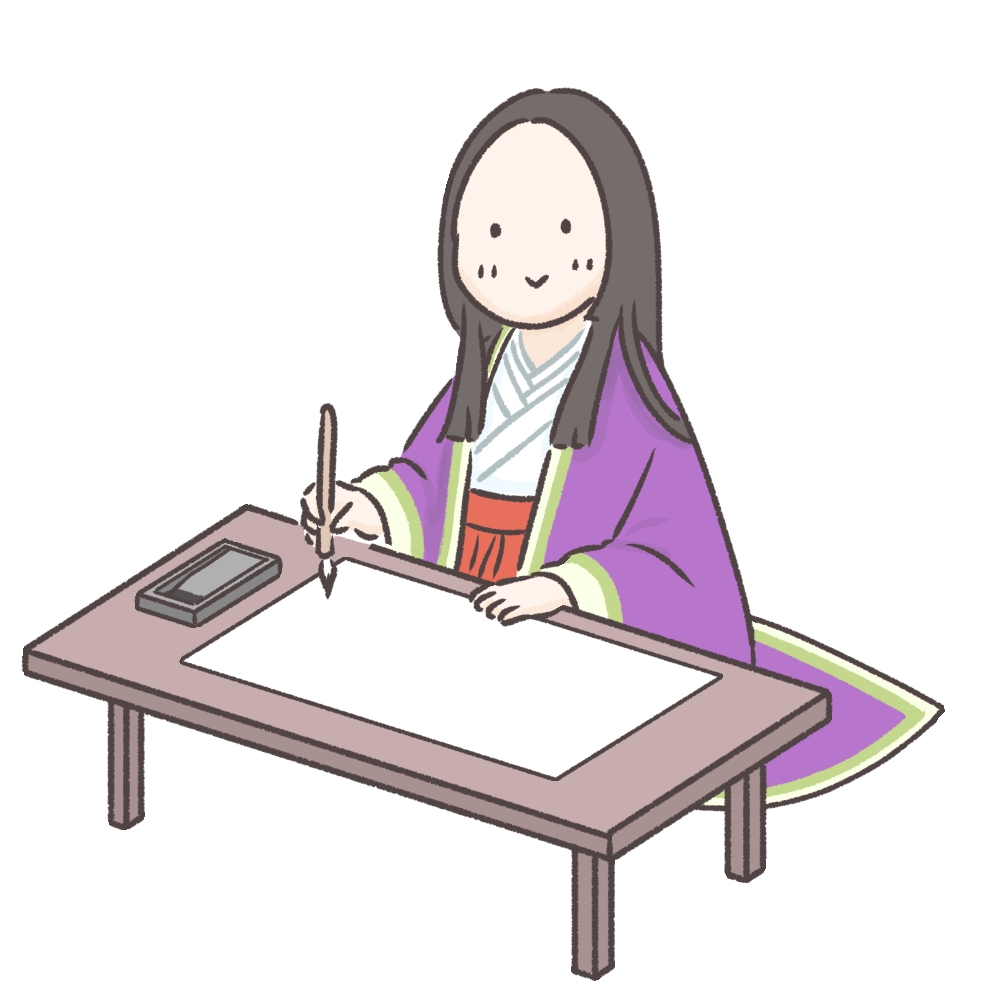
前回は「なむ」の識別について説明しました。(リンクはこちら→古典文法解説⑤~「なむ」の識別編~)
今回は「に」の識別について説明していきたいと思います。
はじめに
まずは「に」の種類について確認しておきましょう。
◎完了の助動詞「ぬ」の連用形(連用形接続)
◎断定の助動詞「なり」の連用形(体言、連体形接続)
◎形容動詞の連用形活用語尾「に」
「に」は他にもありますが、今回は以上の3つの「に」について確認していきます。今回は接続や下につく語で判断しましょう。
それでは識別のポイントを確認しましょう。
【識別のポイント】
「に」の上につく語が
①連用形なら完了の助動詞「ぬ」の連用形
②体言、連体形なら格助詞「に」
③「~か」「~ら」「~げ」や「性質・状態」なら形容動詞の連用形活用語尾
①、②はシンプルですね。上につく単語からすぐに判断することができます。また①の「に」の下には過去の助動詞「き」や「けり」がつき、②の「に」の下には「あり」系列の単語(「侍り」など)つきます。③については古典文法解説④「なり」の識別でも触れましたが、形容動詞の語幹に多い表現をまとめたものです。「清らなり」の連用形「清らに」といった形ですね。
では、実際に確認してみましょう。
例題
1.遠くなりにけり。
2.はた言ふべきにあらず。
3.あはれにおぼえて、
1は「に」の上がラ行四段活用動詞「なり」の連用形なので、完了の助動詞「ぬ」の連用形。また、下に「けり」がついている。
2は「に」の上が連体形なので、断定の助動詞「なり」の連用形。また、下に「あり」がついている。
3は「に」の上が性質を表す「あはれ」なので、形容動詞の活用語尾の一部。
おわりに
いかがでしたか。活用形や品詞が分からなくなってしまった場合は、辞書を引いたり文法のテキストを確認するようにしましょう!
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
春期講習実施中!詳細は下のリンクから!
KATEKYOの春期講習2025「体験からお子様にあった先生が1対1で指導」