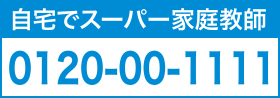KATEKYO知恵袋
【2025最新版】夏休みの読書で差がつく中学受験対策
2025年08月13日

いよいよ夏本番。中学受験を控えるご家庭にとって、夏休みは「学力の底上げ」と「志望校合格への準備」のための大切な期間です。
しかし、受験勉強と同じくらい重要なのが、読書というインプットの時間。とくに近年の中学入試では、読解力・思考力・表現力を問う問題が増えており、受験直結型の学習だけでなく、豊かな知識と感性を育てる読書が大きな武器になります。
この記事では、2024年度の入試傾向をふまえた「この夏に読みたいおすすめ本」と、読書を入試に活かすためのポイントをご紹介します。
中学入試では、国語だけでなく、算数の文章題や理社の記述問題にも読解力が必要です。
単に文章を読むだけではなく、「筆者の意図」「登場人物の気持ち」「背景知識」「要約力」など、複合的な思考力が求められています。
さらに、読書には以下のような効用もあります。
- 語彙力・表現力の向上
- 他者への共感力や社会的視野の広がり
- 記述問題や作文への対応力強化
- 面接時の会話や自己表現のベースづくり
学習効果だけでなく、思春期に入るお子さまにとって「他人の気持ちを理解する訓練」や「世界を広く見る力」を身につける点でも、読書は非常に有効です。
2024年度の中学入試では、次のようなジャンルが多くの学校で出題されました。
物語文学(現代小説・古典)
登場人物の心情理解やテーマに関する考察を問う設問が中心。現代小説では、家族や学校を舞台にした等身大の物語、古典文学では伝統文化や歴史を背景にした作品が好まれます。
説明的文章・論説文
環境、科学、歴史、文化など幅広いテーマが扱われ、論理的な読解力と背景知識が問われます。図やグラフを読み解くスキルも求められます。
伝記・ノンフィクション
偉人の生き方や、科学的・歴史的事実を扱う作品から、人物の価値観や社会への影響を考える問題が出題されます。
ここでは、2024年度の中学入試に出題された作品を中心に、お子さまの読解力・思考力を伸ばす本をジャンル別にご紹介します。
現代小説は中学入試で最も多く出題されるジャンルであり、様々な作品が選ばれています。
『きみの話を聞かせてくれよ』 (村上雅郁)
出題校例: 海城、慶應義塾普通部、聖光学院、駒場東邦、栄東、淑徳与野、早稲田実業学校中等部、渋谷教育学園幕張、開智、他多数
『この夏の星を見る』 (辻村深月)
出題校例: 麻布、開成、雙葉、豊島岡女子学園、早稲田、慶應義塾中等部、早稲田大学高等学院中学部、渋谷教育学園渋谷、他多数
『成瀬は天下を取りにいく』 (宮島未奈)
出題校例: 女子学院、武蔵、浅野、市川、東邦大学付属東邦、立教新座、他多数
『月の立つ林で』 (青山美智子)
出題校例: 浦和明の星女子、立教女学院、広尾学園、高槻、他
古典や海外文学からの出題は現代小説に比べると少ないですが、出題される場合は物語の読解力や文化背景の理解が問われます。
『徒然草』
出題校例: 武蔵、他
『平家物語』
出題校例: 一部の学校
『賢者の贈り物』 (O・ヘンリー)
出題校例: 豊島岡女子学園、他
『星の王子さま』 (サン=テグジュペリ)
出題校例: 一部の学校
『モモ』 (ミヒャエル・エンデ)
出題校例: 一部の学校
説明的文章・論説文は、多岐にわたる分野から出題され、論理的思考力、情報整理能力、筆者の主張を正確に読み取る力が求められます。
『わからない世界と向き合うために』 (中屋敷均)
出題校例: 開成、聖光学院、慶應義塾普通部、麻布、駒場東邦、早稲田、女子学院、雙葉、渋谷教育学園幕張、栄東、淑徳与野、他多数
『植物のいのち-からだを守り、子孫につなぐ驚きのしくみ』 (田中修)
出題校例: 灘、東大寺学園、他
伝記やノンフィクションは、実在の人物の生き方や、実際にあった出来事を通して、学ぶことの意義や社会貢献、困難に立ち向かう姿勢などを問う問題で出題されます。
『世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ』 (ホセ・ムヒカ著/くさばよしみ編)
出題校例: 早稲田、他
『夜は短し、歩けよ乙女』 (森見登美彦)
※これは物語文学に分類されるべきですが、稀に伝記やノンフィクションとしてではなく、「生き方」や「探求」といったテーマに沿って一部が抜粋される場合もあります。正確には物語文学です。
出題校例: 開智、他
『君たちはどう生きるか』 (吉野源三郎)
出題校例: 一部の学校
・上記はあくまで出題例であり、全ての学校の出題を網羅しているわけではありません。
・同じ作品でも、異なる学校で異なる箇所が抜粋されることがあります。
・出版社によっては、過去問分析資料を公開している場合がありますので、そちらもご参照ください。
・最新の傾向としては、発売からあまり時間の経っていない新刊本や、文学賞を受賞・ノミネートされた作品からの出題が増える傾向にあります。
中学受験の国語対策としては、これらの頻出作品を読み込むことはもちろん、様々なジャンルの文章に触れ、読解力、語彙力、論理的思考力を総合的に高めることが重要です。
ただ読むだけではなく、「学びに変える」読書習慣が合格への近道です。
- 目的意識を持って読む
「なぜこの本を読むのか?」を決めておくと集中力が違います。 - 線を引いたりメモを取る
大事だと思った言葉、人物の心情、印象的な場面などに線を引いておくことで、後から読み返しやすくなります。 - 登場人物の気持ちを想像する
「自分だったらどうする?」を考えることで、読解に必要な想像力や共感力が育ちます。 - 要約する習慣をつける
物語の要点を短くまとめる力は、国語の記述対策や面接にも役立ちます。 - 家族や友達と感想を共有する
感想を話すことで内容が定着し、自分の意見を持つトレーニングにもなります。
本を読む習慣を家庭でつくるためには、環境づくりも大切です。
- 図書館や書店に一緒に行く
- 毎日10~15分でも読書タイムをつくる
- 読書記録をつける(読んだ冊数、感想など)
- 家族で同じ本を読む・感想を言い合う
「たくさん読ませなければ」と思う必要はありません。
一冊を丁寧に読み込む体験の方が、ずっと大切です。
受験に直結する勉強にばかり目が行きがちですが、夏休みの読書はお子さまの学力だけでなく、人間力や感性を育てる時間でもあります。
難しい問題に向き合える粘り強さや、他者の気持ちを理解する優しさは、すべて「読む力」から育まれます。
ぜひこの夏、お子さまの関心や志望校の傾向に合った一冊を見つけて、読書の時間を親子で共有してみてください。きっと受験の先にもつながる、かけがえのない学びとなるはずです。